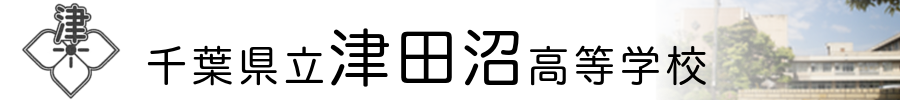「わかりにくい?」授業について 平成30年6月12日
皆さんは、授業を聞いて「わかりにくい」と嘆くことはありますか? あるとすれば、次にあげる例のうちのどのような状況を「わかりにくい」と考えているのでしょうか
① よく聞き取れない(声が小さい、いつも黒板に向かって話しているなど)
② 板書が読めない(字があまりに乱雑、板書の位置等が不適切など
③ 一方的な説明だけである
④ 進度が速すぎる
⑤ 内容が難しくてついていけない
⑥ 苦手意識がある
もしも、例の①~③についてだったら、それは先生が確認してすぐに工夫・改善しなければならないことです。
一方、④~⑥の場合には、自分に原因がないかどうか、振り返ってみてください。
短い時間でもいいから予習や復習をしているか、わからないことをいつもそのままにしてはいないか、難しい・苦手だと決めつけていないかなど、反省してみる必要があります。
中学校でも高校でも、各科目にはそれぞれ目標(習得しなければならない内容)があります。だから、一年間の限られた授業時間数の中で、その目標を達成するためには進度も考えて授業を進め、家庭学習なども含めて工夫して指導しなければなりません。
そもそも聞いてすぐわかるような内容を授業で取り上げる必要があるのか、また、難しいことでも悩み考えるからこそ力がつくのではないか・・・と考えると、極端な言い方ですが、わかりにくいのが授業であり、これにいかにチャレンジするかが大事だともいえます。もちろん、先生もこうしたチャレンジ精神がさらに高まるよう、授業を工夫・改善します。
部活動等では「厳しい練習に積極的に取り組み、実力を伸ばして成果を上げた」などの言葉がよく聞かれます。ならば勉強についても「手取り足取り、懇切丁寧、わかりやすい」と思っている授業で、本当に力がついているのかどうか、考えてみるべきだと思います。
千葉県立津田沼高等学校
校 長 安田 一夫
「高等学校」としての学びの環境づくり 平成30年4月12日
平成30年度が始まりました。津田沼高校にも新入生が加わって、新たなスタートを切ったところです。元気に通学し始めた新入生の明るい笑顔を見ていると、こちらも元気になり、大変うれしく思います。
ほとんどの中学生諸君が高等学校に進学する時代ですが、昔も今も「高等学校」の意味は変わらないと思います。卒業後には、職業に就く者も上級学校に進学する者も進む道はそれぞれですが、社会という荒波にもまれることになるのですから、高校時代にいろいろな経験を積んで(特に「困った」という体験が大事)、自分で課題を解決するために考え、主体的に行動してほしいと思います。
それができる人同士が集まればよいチームもできるでしょうし、みんなで課題に立ち向かっていけば必ず解決の糸口が見つかります。こうした経験は確実に人間的成長につながり、個性の伸長にもつながります。
いろいろなことに挑戦して仲間と共に困難を乗り越えていく。津田沼高校は、こうした学びの環境づくり推進し、本当の意味での「高等学校」と認められることを目指します。
千葉県立津田沼高等学校
校 長 安田 一夫
「困った・・・」という体験こそ大事 平成30年1月18日
「挫折が人を育てる」といいますが、挫折までいかなくても、「困った・・・」という体験はとても大事だと思います。困ったことを解決しようとしてあれこれ考える、工夫する、相談できる人を探すなどなど、いろいろと試み、それが成長につながるからです。
私たちは、困りごとなどなく満ち足りている時には、進んで苦労や努力などしようとはせず、のんびりしているというのが正直なところでしょう。それでいて、何か物足りなさを感じていたりもするものです。しかし、困ったことに直面すると、それを解決しなければなりませんから、頭も体も積極的に動かすし、その動いている時間はとても充実したものにさえ思えます。たとえ完全な解決に至らなくても、奮闘努力した時間は決して無駄にはならず、人間的成長につながります。(そういえば、「失敗は成功のもと」とか「必要は発明の母」という言葉がありましたね・・・。)だから、若い人たちには、この「困った・・・」の体験をたくさんしてほしいと思います。
ところで、心配なのは、この「困った・・・」の体験を知らず知らずのうちに子供から奪ってしまう大人の行動です。大人は、自分が様々なことを体験してきた分、「困った・・・」の解決法をたくさん知っているので、すぐに答えを言おうとする。まして、自分の子供など、大切に思っている者に対しては、つい口出ししたり手を貸したりしてしまいます。
でも、ちょっと待ってください。人が育つには「困った・・・」という体験がとても重要なんです。大人は、(私たち教師もですが)「困った・・・」が重大な事態にならないように見守り、場合によっては解決に向けたヒントを示すぐらいはするものの、極力手助けはしないという我慢の姿勢を貫きたいものです。
中高生の皆さん、「困った・・・」の体験を奪われないようにしてくださいね。自分で試行錯誤する体験を面倒がらず積み重ね、「自立」することを目指してください。
千葉県立津田沼高等学校
校 長 安田 一夫
高校を目指す中3生の皆さんへ!~ 志望校決定に向けて ~ 平成29年10月16日
高校進学を考えるとか、志望校を決定するということは、中学3年生の多くの皆さんがこれから直面することであり、「自分の意志で進路を決定する」という、初めての経験かもしれませんね。夏休みにはいくつかの高校の「学校説明会」に参加したり、「進学フェア」というようなものに足を運んだりしたのではないでしょうか。そして今後は中学校の先生や保護者の方と相談して志望校を決定していく・・・・・という時期なのだと思います。
そこで、私からは、次のことをアドバイスします。
○先輩から話を聞くなどして、その学校の日常の姿を確かめてください。
(先生方が授業を工夫しているか、学校行事は充実しているか、部活動の状況はどうか、生徒指導はしっかりしているか、地域からの評価はどうかなど、聞いて判断する。)
○「行きたい学校」に合格するための努力をしてください。
(はじめから「私のレベルで行ける学校はどこか」という発想ではだめ。入学してから自分に合っていないと後悔する危険性がある。)
○受験は「苦しい試練」ではなく「自分を高めるチャンス」であると考えてください。
(入試で「合格」することは目的(ゴール)ではない。将来に向けての通過点であり、そこから新たな未来が始まる。たとえ思いどおりにいかなくても、それは通過点でのことであり、夢は未来にある。)
津田沼高校は、生徒が主体となって勉強、部活動、学校行事に熱心に取り組み、充実した高校生活を目指す、あなたの本気を応援します!
千葉県立津田沼高等学校
校 長 安田 一夫
「リーダーシップ」って何でしょう? 平成29年8月25日
私たち人間は、少なからず集団で行動することが多いです。しかし、集団の中の一人一人はみんなそれぞれ個性を持っているし、考え方や行動パターンなどもみんな違います。
だから、その集団をまとめるためにはリーダーが必要で、そのリーダーが「リーダーシップ」を発揮してこそよい集団なのだと考えられています。
ただ、私はちょっと心配なことがあります。それは、「学級委員長がリーダーシップを発揮し、よりよい学級をつくってください」とか「今はリーダー不在の社会と言われていますが、強いリーダーシップを発揮できる人が出てくることを期待しています」などというように、何かとても他人事のような言い方を聞く点です。
現代の社会では、私たちは個人としても、あるいは集団の一員としても、実に様々な課題、とても複雑な課題に直面することが多いと思います。このような状況の中で、集団を一人のリーダーがまとめるなどというのは難しいと思います。リーダー的な人物は必要にもせよ、集団をつくっている一人一人がリーダーを積極的に支えたり、また、ある場面では、「ここは自分がリーダーの役割を果たそう」という心構えをみんなが持っていないと、その集団は崩壊してしまうのではないでしょうか。
「リーダーシップ」というのは、リーダーという一人の人が「私についてきなさい」と、集団を強い力で引っ張っていくことだとは限らないと思います。集団の一人一人がお互いによくコミュニケーションし、自分の果たすべき役割をそれぞれ考え、その役割を果たしてリーダーを支えていくことこそ大事だと私は思うのです。
千葉県立津田沼高等学校
校 長 安田 一夫
「オリジナリティー」と「学ぶ力」 平成29年7月24日
私は小学生のころプラモデル作りが大好きでした。小遣いやお年玉をためてはプラモデルを買い、飛行機や船、自動車など、次から次へと作りました。しかし、パーツは一色で、デーカールを貼って多少の色やデザインを追加するだけなので、だんだんとそれに飽き足りなくなりました。模型屋さんに飾ってあるような、今にも動き出しそうなものを、自分で塗装から何から工夫し作ってみたくなりました。よりリアルなものを仕上げるためには写真などの資料で研究し、パーツを自作して追加することもありました。こだわりを持つことは大変ですが、「人と同じじゃつまらない」という気持ちに突き動かされ、飯を食うのも忘れてプラモ作りに没頭し、親に怒られもしました。でも、「自分だけのオリジナル」を仕上げた時の達成感と優越感は最高でした。
オリジナリティーへのこだわりは、私が教師になって授業づくりをするにあたり、多少なりとも役立ちました。生徒に教材を選択させたり(定期試験に選択問題を導入)、生徒同士相談させる授業の仕組みをつくったり、生徒に試験問題をつくらせたり、独創的な授業づくりを目標としました。そうした取組は先駆者もいたと思いますが、自分なりの工夫をいろいろ模索しました。生徒に「自分で工夫した学び」を体験させたかったのです。
ところで、中・高生諸君は、今、自分が受けている授業をどう思っているのでしょうか。先生が「今日のねらい」から始まり「今日のまとめ」までを丁寧に板書し、教具も工夫を凝らし、至れり尽くせりに指導してくれるのがいいと思うのでしょうか。でも、それに慣れきってしまい、自分で理解する工夫や忍耐(「わからない・困った」に耐え、自分で解決しようとする姿勢)を忘れてしまったら、本当の「学ぶ力」が育つとは思えません。
中・高生諸君には、将来に渡って役立つ「学ぶ力」を身に付けるため、大いに悩んでもらいたい。人に頼って与えられた知識は、すぐ忘れるか、すぐ役に立たなくなるかです。「与えられる学び」はプラモ作りでいえば、誰かが、研究も改良も塗装も済んだ「完璧なパーツ」を準備してくれ、あとはそれを組み立てるだけというのと同じ。失敗はないけれど、オリジナリティーはないし、作る醍醐味も達成感もあり得ない。だから、進歩もない。
学校教育の在り方が問われる中、先生が授業を工夫することも大事ですが、生徒が自分なりの学習の工夫をして、「学ぶ力」を伸ばすことの方がもっと大事だと私は考えます。
千葉県立津田沼高等学校
校 長 安田 一夫
「コミュニケーション」について 平成29年6月23日
「コミュニケーション能力を育成する」・・・などとよく聞きますが、どうすればその能力を育成できるのか、これはなかなか難しい問題ですね。
「これが答えだ」というのはないにしても、良好なコミュニケーションをするためには欠かせない三つの力(能力)があると私は思っています。「伝えたいことを明確にする力」「伝える相手を理解する力」「伝わったかどうかを評価する力」の三つです。これらの力を向上させることが、相手との上手なコミュニケーションにつながるのだと思っています。
例えば、人に仕事を頼むとします。成果を期待するならば、まずは自分の求めていることが明確に伝わるように工夫しなければなりませんし、頼む相手の力量や個性を理解し、自分の依頼がしっかり伝わったかどうか確認しなければいけません。
「○○さん、この週末に会議で使うので、うちの課の事業進捗のこの資料、25ページあるんだけど、これをワンペーパーにまとめてね。ではよろしく。」こんな頼み方では相手は理解できません。これは頼む方の配慮が足りないのです。
「○○さん、この週末の会議で、部長にうちの課の事業進捗状況について報告するんだけれど、この25ページの資料を読んでまとめたA3のワンペーパーを作ってくれないかなぁ。君は分析力に優れているしパソコンも得意だから、今後、事業を進める上で課題となることも示し、必要に応じて図やグラフなども盛り込んで作ってくれるとありがたい。部長は~~のことも知りたがっていると思うので、そのデータを前面に出してPRしてほしいな。どう、作れそうかい?質問があったらどうぞ。」というように頼めば、意図がより確かに伝わるでしょう。
社会に出ると、上手なコミュニケーションができるかどうかで仕事の効率が大きく変わってきます。私の経験上も、後者のような指示のできる上司はとてもありがたかったし、尊敬できますよね。かくあらねばと、私も反省するところです。
千葉県立津田沼高等学校
校 長 安田 一夫
「表と裏」の話 平成29年5月29日
「あの人は表裏のある人だ」とか、「表の顔と裏の顔」など、「表と裏」ということは、あまりよい意味では用いられないのが普通です。
でも、私たちは、表だけで生きているとか、裏だけで生きているということはないと思います。人には知られたくないことは表に出したくないという方が人間らしいし、人間関係をうまくやっていくために、本当の自分とは多少のズレがあることを表にしているということは、誰しもやっていることではないでしょうか。それが人をだましたり、悪に手を染めるためというのはあってはならないですが、表の自分と裏の自分というような二面性は自然なことで、自分自身それを認めるとともに、他人だってそういうことがあると理解する方がいいのではないかと私は思います(人の心がわかるということだからです)。
ところが、困ったことに、今日の社会ではこのような人の心の繊細さが理解されず、本人が意図しないのに裏側がさらけ出されてしまう危険が増していると思うのです。個人的なメールで心の内をつぶやいたら、自分の知らないうちに世界中に拡散してしまったなどということが起こってしまう。人が、というか、世界がというか、信じられなくなってしまうなどということも、決して大げさではないでしょう。
表があれば裏もある、その裏側を他人が興味本位でつついたり、自分の認識が甘く、知らないうちにさらけ出してしまったりということがないよう、マナーやモラルというものを徹底しないといけない。そうでないと、私たち人間の心は今後どうなってしまうのだろうかと心配です。
私たちは、他人を理解しようとする気持ちと、そっとしておいてあげようという気持ちのバランスを考えながら、他人の心を思いやれる人にならなければいけませんよね。
千葉県立津田沼高等学校
校 長 安田 一夫
「あいさつをしない」理由 平成29年4月28日
「あいさつをする」理由は、説明しやすいです。
- 相手に対する礼儀
- 自分の存在をアピールする
- 相手も自分も気持ちよくなる
などなど、自己と他者との関係を取り持つことを説明すれば間違いないです。
そして、わかりやすい分、人間関係上での大きな誤解は少ないです。
でも、「あいさつすれば何とかなるだろう」ぐらいの気持ちでも「相手は私を認めてくれているんだな」「彼は私に好意的なんだな」と思われるかもしれないから、「プラスの誤解」の可能性はありますね・・・・・。
これに対し、「あいさつをしない理由」について説明するとなるとちょっと複雑です。
- 気付かれたくない、目立ちたくない、自分に自信がない
- 親しくもない人と言葉は交わせない、他者との関係には慎重である
- 他人には無関心、人間関係嫌いである
- 相手を認めたくない、敵意を抱いている
- 子供じゃあるまいし、あいさつなんて・・・・・
などなど、多岐にわたります。見方によれば、あいさつしない人の方がごまかしがなく、正直であるともいえるかもしれませんね。
でも、理由が多岐にわたる分、相手からは「マイナス面」で誤解される可能性が高いと思います。本当は目立ちたくない理由で、あいさつしないのに、「この人、私のことを無視するんだな」「彼は私に敵意を抱いているのかもしれない」などと誤解される可能性もあるから、危ないです。
私は、「あいさつ」はとても大事だと思っていますが、その理由は、あいさつするとお互い気持ちがよくなると信じているからです。
千葉県立津田沼高等学校
校 長 安田 一夫
新学期のスタート、新しい自分 平成29年4月14日
今年は、思いのほか桜が長い間咲き誇り、春を長く感じることができましたね。
そして、やっぱり春は新学期のスタートだと実感できるのではないでしょうか。
中学校でも高校でも、入学式が過ぎて数日といったところでしょうか、新入生は新たな環境で、また、2・3年生も、後輩たちを迎えてそれぞれの学校生活が始まりましたが、まさに、そんな今、私は皆さんに「新しい自」ということについて考えてもらえたらいいなぁと思います。
私の言う「新しい自分」というのは、自分のために、人のために、これまでできなかったことを何かやってみるということで、決して大げさなことではないです。
新入生は、期待をもってそれぞれ中学校・高校に通っていると思いますが、その期待がしぼまないように。もっと、ふくらむように、勉強へのこだわり、委員会活動、部活動、習い事、何でもいいと思います。これまでとは少し違った「新しい自分」をイメージしてみてはいかがでしょうか。
そして、2・3年生は、これまで自分がやってきたこと、できなかったことを振り返って、自分のよさをもっと伸ばせるような何かを探し、挑戦してください。
新たに始めたことの毎日の積み重ね。それは、やがて大輪の花を咲かせることになるでしょう。そんな自分に自信がもてるようになるでしょう。
頑張れ、中・高生!
千葉県立津田沼高等学校
校 長 安田 一夫
「予習」する習慣が将来ものをいう 平成29年3月17日
「開かれた学校づくり委員会」で、委員の皆さんに学校評価をしていただくとき、学力向上には「予習」が大事だということをご指摘いただきました。私は改めて「なるほど、おっしゃるとおり」と思いました。
- きちんと予習をさせない(生徒が「予習をしなくてもいいんだ」と思っている)授業では、緊張感が生まれない。だから学力が定着しない。
- 「予習をしなくてもわかる授業」というのはレベルが低いのではないか?「わかりやすい授業」というが、本来、学習するというのは「難しいことを克服する」ことだ。
- わずかな時間でもいいから、授業の準備(何を学ぶのかをあらかじめ確認する)をすることが大事だ。
- 人に会うとき(仕事の打ち合わせや商談などなど)でも、相手のことを調べずに会っても上手くいくはずがない。「予習」をしてこそ成果があがるのだ。
こうしたご意見をいただいたのだが、とても勉強になりました。
私たちは、毎日栄養を補給し、身体を維持し健康を保っています。同様に、学力の定着・向上というのも、毎日少しずつの積み重ねだと思います。一気に食べたら消化不良を起こすにきまっています。毎日の学習習慣、特に「予習」の習慣をつけておくことは、将来、社会人になった時にものをいうんです。
忙しい社会人になってから、こうした習慣づけをしようとしても、今の何倍も苦労することになります。
千葉県立津田沼高等学校
校 長 安田 一夫
「生きる力」を高めるために 平成29年3月2日
社会は変化していくものです。私も「激しく変化する今日の社会に対応するため・・・」などと言ってしまいますが、今も昔も社会は常に変化していくものだし、その変化が激しい時こそ、様々なチャンスがあると、前向きに考える方が賢明だと思います。
しかし、常に受け身で過ごしていたら、そのチャンスも見逃していくでしょう。誰かの指示を待っていたら、決してチャンスは訪れないでしょう。だから、人に頼らない生き方、挫折を恐れずチャレンジする生き方、頑張っている人と共に頑張る生き方が大事です。
そんなことは、本当は誰でもわかっているんです。でも、なかなかそれができないから悩むんですよね・・・。
学校生活で、「生きる力」を高めるために、私が推奨するのは、次の七つ。
- 「大人のあいさつ(人間関係をつくるため、自己PRをするためのもの)」をすること
- 何事も、まずは「やってみよう!」と取り組むこと(失敗はつきもの、すぐにあきらめたりしない。「できない」ことの言い訳はやめる)
- ときどき自分と向き合う(客観的に見て自分をチェックする。悪い点は素直に反省し、自分の得意なもの優れた点を伸ばせるようにする)
- 他人を観察し、よいところを見つけてほめること(他人のあらさがしは簡単だが、ほめるのは結構難しい。それができれば自分にもプラスになる)
- 本音で話し合いができる友人をつくること(自分を本気で批判してくれる人が理想)
- 友人や先生を協力者にすること(自分の利益のため、都合のよいときだけ利用するのではない。本当に困ったときに助けてくれる)
- 自分で確かめた情報のみを活用する(情報をすぐに信じてしまうのは危険。せめて信頼できる人に聞いて確かめるべき)
これらのことは、社会で成功している人は必ず意識しているでしょう。
多少の勇気がいりますが、やってできないことではありません。
千葉県立津田沼高等学校
校 長 安田 一夫
「元気な学校づくり」を推進します! 平成29年2月9日
高等学校では、生徒が主体的に学び、活動し、自分たちで「学びの環境」をつくっているところに価値があると思います。先生方は、その環境づくりを後押しするのが学校運営の基本です。津田沼高校が、こうした理想の学舎でいられるよう、改善に努めています。
その改善に向けての合言葉は、「元気な学校づくり」です。学習指導、生徒指導はもとより、学校行事や進路指導(早い時期からの進路意識の向上)、部活動指導(文化部活動と運動部活動の「文武両道」)など、さらに充実したものにしていきたいと考えています。
そのためには、「自分の力で高校生活を充実させるぞ!」という生徒諸君の強い意志や、保護者、地域の皆さんのご理解・ご協力が欠かせません。よろしくお願いします。
折しも「高校入試」の時期を迎え、多く中学生の皆さんが本校を目指してくれています。どうか、この津田沼高校に入学し、「元気な学校づくり」の一翼を担ってください。
千葉県立津田沼高等学校
校 長 安田 一夫