このページの内容(下の項目をクリックしてください)
学校の概要
1975(昭和50)年に男女共学の普通科高校として開校し,「進取」「創造」「友愛」を校訓とし,「生徒の潜在能力を拓く」をスローガンにする学校です。
生徒一人ひとりの進路希望の実現と校訓の内容の実践により,豊かな人間性を育成することを目標としています。
校 訓
- 進 取 - みずから進んで事をなす。
- 創 造 - 主体的に考え,新たなものを創りだす。
- 友 愛 - 友を愛し,人を愛す。
校 章
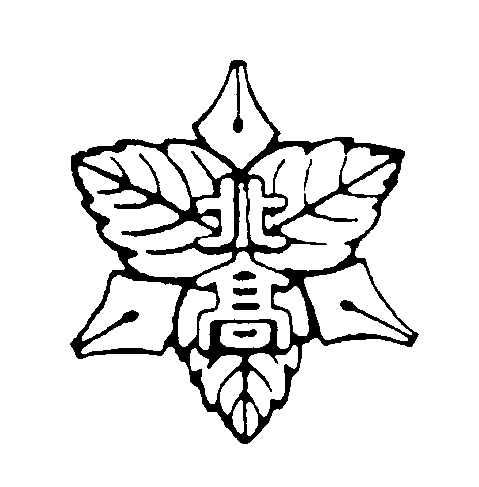
“北斗之尊”ということばがある。天の中心に位置する北斗星になぞらえて,多くの人の中で最も尊い者を示す語である。「北」の字をその名に負うわが校の生徒も,この気概をもって向上を目指したいものである。
校章には,まずこの「北高」の文字を中心に据えた。そこから六方に放射する線は,天・地・東・西・南・北に雄飛する若者の意気を象徴する。
また全体の輪郭がかたどる「水」の字は,あらゆる生命力の源泉でもある。そこに組み合わせた図案では,若葉によって健康を,ペンによって英知を代表させている。次代をになう健全な若人の育成に願いをこめたものである。
学校教育目標
- 志を高く掲げ,文武両道を目指すとともに,心豊かな逞しい生徒を育成する。
- 全ての教育活動を通じて,生徒一人ひとりへの進路保障の具現化を図る。
- 国際理解教育を推進し,国際的な視野を養い,国際的教養を身につけさせる。
- 保護者や地域から信頼される学校づくりを目指す。
令和2年度千葉県立千葉北高等学校教育指導方針
| 教育目標 | ||
| 1 民主的な国家及び社会の形成に役立つ心身ともに健全な人間の育成 | ||
| に努める | ||
| 2 相互信頼の上に立ち、責任と規律を重んじ、勤労意欲のある人間の育 | ||
| 成に努める | ||
| 3 社会人として必要な知識・技能と創造的な思考力とを身につけた人間 | ||
| の育成に努める | ||
| 校訓 | ||
| 進取 みずから進んで事をなす | ||
| 創造 主体的に考え、新たなものを創り出す | ||
| 友愛 友を愛し、人を愛す | ||
| 重点目標 | ||
| 社会の変化に対応し活躍できる力を高め、「夢」の実現に向けて目標を設定し努力する生徒の育成と魅力ある学校づくり | ||
| 1 学習、部活動、学校行事を通じて「自主自律の精神」を育む | ||
| 2 感性を磨き、互いに尊重し協力し合い、思いやる「豊かな心」を育む | ||
| 3 地域から信頼される「憧れの学校」、保護者が「安心な学校」を | ||
| 目指す | ||
| 目指す生徒像 | ||
| 社会に貢献できる資質・力量を有し、将来を見据えた適切な目標を定め、「夢」の実現に向けて持てる力を存分に発揮し、努力する生徒 | ||
| 生徒に育成すべき資質・能力の三本柱 | ||
| ①人間性の涵養 | ||
| ・学校生活すべての場面で、考え方、立場、性格や価値観の異なる人と 相互に理解し、共存し合える心、態度の涵養 | ||
| ②知識・技能の習得 | ||
| ・未来を生き抜くために重要で必要な知識・技能の習得 | ||
| ・「夢」実現へ向けて基礎力の充実と専門知識の習得 | ||
| ③思考力・判断力・表現力の育成 | ||
| ・未知の課題に対応すべく学習したことを、自ら調べ、考え、他人に 伝えることができる意欲や能力の育成 | ||
| ・「自調」「自考」「自行」の実践(家庭学習の励行で深い学びへ) | ||
| ・「学習」「部活動」「学校行事」を通して培う意志力と実行力の育成 | ||
| 目指す学校像 | ||
| 生徒自らが「夢」の実現に邁進できる環境整備と職員全体の協力体制のもと個々の生徒を大切に支援する学校 | ||
| 生徒支援のための取組事項 | ||
| ①学校改善プロジェクトチームの設置 | ||
| 学校の将来を見据え、学校全体の方向性を協議する組織の設置 | ||
| ②職場環境の整備 | ||
| 組織の整備・慣習を見直し、多数の経験豊富な職員の指導力の | ||
| 継承 | ||
| ・各分掌の仕事の区分けの明確化 | ||
| ・学年・分掌ごとに仕事分担の見直し(複数重複対応で仕事の軽減) | ||
| ・部屋及び施設管理方法の確認(鍵の管理及び施設の利用規約) | ||
| ・職員の相互に助け合う心の育成(介護、病気等の事情を複数対応 | ||
| で軽減) | ||
| ③学習環境の整備 | ||
| 授業力向上による「主体的・対話的で深い学び」の実現 | ||
| ・授業力向上研修の有効活用 | ||
| ・相互の授業参観の推進 | ||
| ・外部公開授業、実践研究会等への積極的参加 | ||
| ・生徒の知的好奇心を高める工夫 | ||
| ・各授業における振り返りの重視 | ||
| ④キャリア教育の充実 | ||
| 総合的な探究の時間や各行事等を活用(段階的、継続的、計画的 | ||
| 指導) | ||
| ⑤情報活用の改善 | ||
| 迅速な情報発信(生徒、地域、保護者への情報提供で安心な学校) | ||
| ・非常変災時の学校運営状況の発信(迅速に) | ||
| ・学校行事、部活動からの状況報告(明確に) | ||
| ・普段の学校の様子(授業)、学校通信等の発信(全てに) | ||
| 校内情報活用の改善による成績等の情報の一括管理 | ||
| ・指導要録、調査書等の一括管理(正確に) | ||
| ・県システムへの段階的移行 | ||
| ・情報掲示板の活用(昇降口に設置 生徒会、部活動、分掌等) | ||
| ⑥生徒指導の継続 | ||
| 整容指導の継続こそ自由と規律を尊重し評価される本校の必須 | ||
| 条件 | ||
| ・指導体制の確立(職員の同一歩調) | ||
| ・生徒の人権の尊重(言葉遣い、距離感) | ||
| ⑦教育相談の充実 | ||
| 体系的な教育相談による心の不調を訴える生徒の増加への | ||
| 組織対応 | ||
| ・定期的な教育相談委員会の情報交換 | ||
| ・個々の問題を組織で対応 | ||
| ⑧国際理解教育、高大連携事業の推進 | ||
| ・短期留学希望者への指導 ※次年度再開に向けて | ||
| ・高大連携事業強化の拡張 | ||
| 保護者の方へ | ||
| 生徒への大切な一義的支援者、学校への支援のお願い | ||
| 情報収集 | ||
| ・生徒との対話の増加 | ||
| (専門的な教育相談、セクハラ相談の窓口の周知) | ||
| ・学校の情報はHPや連絡文書で、担任は学校の大切な窓口の役割 | ||
| 興味関心 | ||
| ・進路決定の相談は、保護者の関わりも大事(金銭的支援を含む) | ||
| 地域の方へ | ||
| 小中学校、自治会や団体等との積極的な情報交換と連携 | ||
| ・小中学校との連携(緑ンピック参加、授業参観等) | ||
| ・地域への貢献(ボランティア清掃作業、演奏会、パフォーマンスの実施) | ||
| ・情報発信の強化(的確な情報発信と中学生への情報提供) |
