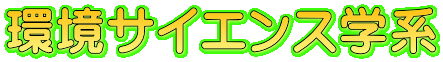
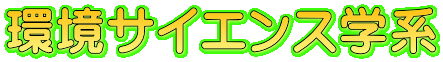


・ 環境をテーマとする学習を取り入れ,学校周辺の水質調査,ビオトープの維持管理等を行います。
(環境学の授業では、ホタルを育てたり、古代米を収穫し お餅にして食べるなどの授業があるんだよ。)
・ 手賀沼を中心としたフィールドワークや環境をテーマとした課題研究を通して、環境問題を専門的に勉強していける力を身につけます。
・ 実験や観察が好きで、理工系の大学・専門学校に進学しようと思う人に向いた学系です。
環境サイエンス学系の卒業生の声はこちらから
 |
 |
 |
||
お湯をはって消毒します。 お湯を何度か入れ替えます。 |
||||
 |
 |
 |
||
混ぜています |
最初はこのような感じ。 米を蒸したものです。。 |
|||
 |
 |
 |
||
はじめは押しながらこねます。 こうすることで、米粒をつぶして 食感をよくします。 |
搗き始めます。 最初は軽く、徐々に強くします。 |
そろそろできあがるかな? 餅とり粉を準備します。 |
||
 |
 |
 |
||
| 親指と人差し指で○をつくって ちねります。 |
||||
 |
 |
|||
| 美味しい!みんな口いっぱいに頬張っています。 あんなにたくさんできたのに、1つ残らず全てたいらげました! |
||||
 |
 |
 |
 |
|||
| 干して乾いた稲です。 田んぼごとにわけてあります。 |
今日からもみ落とし。 竹を使ってで手作りした道具で 行います。 |
何本かずつ、 竹の切れ目に差し込んで 引っ張ります。 |
 |
 |
 |
 |
|||
| 手でも出来るけど、 痛いんだよね… |
もくもくと、よく集中して 頑張りました。お疲れ様でした。 |
 |
 |
 |
 |
|||
| 稲穂が垂れてきました | 刈り方や干し方を 教えてもらいます |
鎌の使い方は大丈夫かな? | 刈った稲は、数束まとめて ひもで縛ります |
 |
 |
 |
 |
|||
稲刈り前に田んぼの 水を抜くのを忘れてしまいました |
こんなにドロドロです。 足がはまって動けない! |
素早い動きです |
まとめて運びます |
|||
 |
 |
 |
 |
|||
フェンスにかけて干します |
水分量が14%くらいになるまで このような形で干して置きます |
稲刈り後の田んぼです |
きれいに片付けて 作業が終わりました。 次は籾落とし、 2週間後くらいです。 |
|||
 |
 |
 |
 |
|||
| 恐竜の化石模型です | この隕石は31kgもあります | クイズに答えています | 実際の化石もありました |
 |
 |
 |
 |
|||
| 実際の動物の毛に触れられます | 環境問題も学べます | 動物の視野が体験できます | DNAの構造がよくわかります |
 |
 |
|
| 実はこれ、全部貝でできています | 普段何気なく食べているアサリの拡大模型です |
 |
 |
 |
||
| 今年は田んぼを1枚増やしました。 収穫量アップをめざします。 |
ひもを目印にして、 まっすぐになるよう植えます。 |
秋に収穫します。 もちつきをしておいしくいただく予定です。 |