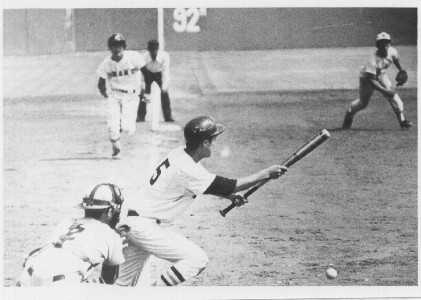@ì ÌnÝÍA¾¡34N5Å ÁÄAJZÌ1ãAZFïðݧ·éÛÌæPÔÚÌxÅ Á½B
@sÅÍAì Í·ÅÉ{[gÆÆàÉAêAîcAcA¾¡w@ÈÇÅsíêÄ¢½ãÌÔ`X|[cÅ Á½ªAܾSIÉÍy¹¸AæêñÌêOíªsíê½ÌªA¾¡39NÅ Á½Æ¢¤©çA»ÌTNOAcÉÌêwZÅì ðݧµ½ÌÍAëìZ·Í¶ßAæ©Ìmªì Éw¶X|[cƵÄÌ¿lðFßıü³ê½àÌÅ ë¤Bµ©µA³ì ÍOÌX|[cÅ èAðjÍóAeZÆàÉw±ÒɱƫAZpÌyàLyÎÈ©Á½àÌÆvíêéBR̯ÉjÜê½nÍȨ³ç̱ÆÅ Á½ÌÅ éB
å³ú
@å³ÉüÁÄAðqÌÉì
ÉnBµÄ¢éÒiCMÌߧà»ÌêlÅ Á½jà ÁÄACÝÅLb`{[ÈÇðµÄyµñÅ¢½ªA{Z¶kàA»ÌZÉ£¹çêÄA»¤¢¤l½¿Ìw±ðó¯éæ¤ÉÈèA¾ñ¾ñyµAZëÅàAñhɶðSÉ©ÈèÉsíêéæ¤ÉÈÁ½BñhɶÎ{Z¶ÌZàÎRÌÍlÈÇÍAåw¨àµëZFïÉc³êÄ¢éBå³4NÌÉLµ½å¬wÆÌÎRí౤µ½úÉsíê½ÌÅ éB

@å³11N²ëAìzÉiA¬ÎìjÉݾÌ{Z²Æ¶A¡Li11ñ²jAì±i13ñ²jAéØ_i15ñ²jAi½êà_¹ÌOBÅ èAñhÉãì
ÌûÅàÒÒÅ Á½BjÈǪSÆÈèAì
Ì»²ð}èAàðWßÄå³12N4Aì
pïê®ð¢»ë¦Aì
êð®õµAƵÄÍ·Î絧hÈÅè®obNlbgðĽB»ÌSÌÌÖsÍA³VmA¡Í20mÙÇ èAobN{[hÍú³UcmÙÇÌÂð2m̳ɣèãÍàÔÅ Á½B
@êwúÌÔÍA©È¬ÅobeBOâLb`{[ðµA[àæmç¸ÉûKðµ½èµÄ¢½ªAñwú©çw±Òðµ«{iI®Éüé×91úA»Ìï®ðËAöx½ðutƵÄì
ÉÖ·éubðµÄ¢éÅÉNÁ½ÌªA©ÌÖåkÐÅ Á½BöÍêuɵÄsAÌqÆÈèAwZͪAì
DZëÅÍÈANÉéàì
êÍÞØuêÆ»µAì
Ì»à·×ÄäjZÆÈÁĵÜÁ½ÌÅ éB
@ºa6NAVZɪvH·éÜÅAobNlbgΩèÍóµcèA»ÌOÍêçAà@ÌWêÅ Á½B
à@íO̲ƶÉÍðàðvµÈ¢ªAÅ㶪º¶SõðW³¹ÄÀç¹A»êðæèÍÝAl̶kðêlêlļµÄN§³¹Aà@µÉÍS§ÙðÁ¦½B
@»êÅàAºa3NÉÍAYÓGvèðiµÄ©ÈèÍÈ`[ª èAêN¶õÍ20¼ðz¦éÆ¢¤·µÅAÌOrÍmX½éàÌðví¹½ªA¬ìZ·Ì³çûjÉí¸A§ºåïÌoêͩȦçêÈ©Á½B
@»êÉÁ¦AVZÉzªnÜéÆAì êÍDíêAûKêÍÀ[ÌZëðØè½èA250gbNÌà¤É_ChðݯģZƯ·éÆ¢¤LlÅ Á½B»Ìæ¤Èt«É èȪçAðãÌõÍîMÉR¦A§ºåïoêðuµ½ªA¬ìZ·ÈÌûjªiópªêAÉíúÉËüµ½B
@ºa16A17N²ëÍAVäèðSÉìAÖªÈÇ̼èA¼ÉδAÀAöARûARºAgcA¬ÑA´ÈÇÌÍÈo[ð»ë¦AçtªðÝA§ºÅà`NXÅ Á½çttÍAçtHÆÈÇÆÝpÌðµÄ¢½ªA§ºåï»Ìà̪Aí̽ßAºa16NÈ~~ÆÈÁ½B

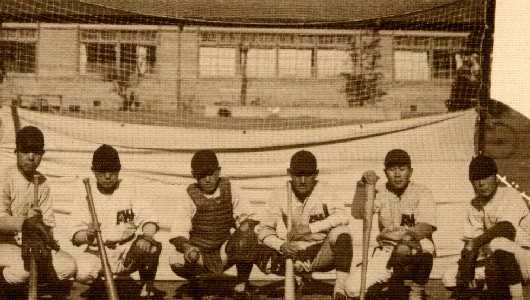
ºa13N̲ÆAoæè
@síãÌÉx̬ÍûܽàÌÌA±Ì±ëÍܾ¡IoÏIÉsÀèÈ㪱¢½ªAì ÌÄͱÆÌÙ©©Á½Bºa22N§ºåïoêÌÍAíÅSsðiµ½àÌÌA»ÌNÌHÍ·ÅÉ̼åZÆÝpÉí¦éæ¤ÉÈèAºa23N©ç26NÉ©¯ÄÍANtÄḨºOåïÉíoê·éÀÍZÌñÉüÁÄ¢½@iÍAtHÍíÑÉæéI²ÅAÄåïà\Iª èA{åïÉoê·éwZÍÀçêÄ¢½jB
@Xq©çXgbLOÜÅÅê³ê½³íâ©Èjz[pÅ}i[ÌdzÆCÌüÁ½LrLrµ½v[ðµA»Ìã²ÆÉ·³Ü¶¢Î©èÌÅ_ðUÁÄA§Z EÉXÉVµ¢ùðª«NµÄ¢Á½ÌÅ Á½B
@íOì³ê½ÌÉðjÍNðdÊêÇâ¦Ì̽µÄAç´ÌvÐôtHA¡µòôÌúé@V»ÌÓC¸VÌ@©Ì®úɽé©ÈÆ¢¤êߪ éªAܳɱÌãͱÌÌÌÊèÅ Á½ÌÅ éB
@³ÄA±±ÜÅÉÁ½vöð¢Â©°ÄÝæ¤B
@ܸæêÉÍA¢¤ÜÅàÈsíÉæéãÌϻŠéBÁÉ{ZÅÍAíO̬ìZ·ãÈÌì }³ô©çÌðúª°çêéBíO©çÌæy½¿ªBEµÄ¢½GlM[ª±±ÉêCÉJÔµ½Ïª Á½B
@ ܽA»ÌãÌϻɺÁÄ`±³çÆÈÁ½V§wªA±¼ÁÄì ÉÍðüêéæ¤ÉÈÁ½±Æà°çêéBAUR§@ì Ωèª@ÈèÆ¢¤ìöª èA»êÍì ÉäµÄ³çÌàeªµáºµ½±Æðç÷Á½àÌÅ Á½ªAÀSàewZÌì MÍ·ñÅ Á½BÁÉn³ÌkðwiãÉÙRñj@Í@åw©çå«Ì¬ÑAÖªiãÌåmÄÂjFºÈÇZåwÅL̼Ièðµ«A»Ìw±ð®ÈÇAÙíÈMCÅ Á½B¼ÉàÛcAâäA[ìAßÃAÙRiãÉÙRêjÈǪ±«ASswåïÉàCªÝȬÁÄ¢½B
@{ZàOL@åwIèÌw±ðó¯AÌì Zp̱üªxüãÉå¢Éð§Á½ÌÅ éB
@ܽÌÚâÉÍA§àÅ̷༷¦Ì©Á½ìû·ðMªÉAåãì ÌIèÅ Á½òcÄÂiãÉçtZ·ASìAï·jA{ZíOÌêïãIèÅ èAOLÌÌìÒÅà ÁÄÌ»²ÉÙíÈ·OðÂöR[`ª¢Äµ¢ûKɾ¯éêÄ¢½ÌÅ éB
@³ÄA»ÌÌ»²ÉÍáQªÈ©Á½óÅÍÈ¢B
@»ÌæêÍAÌWÌèÉïÍÉßÄRµAiºaQUNxÌïÍ46ç~Å Á½Bj{[âobgÌæ¤ÈÁÕi·ç«É¦¸A{[Í ª·èØêÄàAõªèª¯µÄOOɽxàJèÔµD¢¹ÄgpµÄ¢½Bjz[AXpCNAO[uÍSÄ©ÈSÅ Á½ªAªïÜÅS³¹éÉÍÀxà èAåïÉQÁµÄÂÉÍÁÄàAªïÉsÀª èAɵ©äµÆ¢¤Æ±ëÅ Á½Bª¦ÌÕçÉÍì ÌXðoµAåï̽ÑÉASsàeðÁÄDÓðñ¹éûX©çñtð®LlÅAoðS·éìû·ÌêJÍÀåïÅÍÈ©Á½B^®ï®©çÌØ઩³ÝAÚâÍ»ÌXæðð¯ÄÊé±ÆàµÎµÎÅ Á½Bì ÉðɵÜÈ¢½ÌûXÌÅàAÁÉåJ`CAÜØcÛi1ñ²jÈÇÌÏçʪȯê΢©ñÆ൪½¢úª±¢½B
@»ÌãAOhÍ·A250mgbNÌà¤Éݯçê½_ChÉyðüêÄ®õ·éïp·çàAwZÉÍxo·é]TªÈ©Á½ÌÅ éB»Ì½ßçõûKÍv¤ÉC¹¸A¤ã£ZÌgbNÌêðØèÄÂlÂlÉÒmbNð¹é̪ÖÌRÅAǤµÄàÅÍAèÍÉéûKÆÈéÌÍ~Þð¦Ê±ÆÅ Á½ÌÅ éB
³ÄAºa23NÈ~ÌíÑðÈPÉLµÄ¨±¤B
ºa23NVASwZì
åïçt§\I
@@@oêZ@\Ið²¢½PUZ
@@@@êñí@@{Z@10A|0@å½ì
@@@@X@{Z@3|2@sìH
@@@@@@{Z@0|1@¬c
@@@@i±ÌNA@¬cbqoêj
ºa24N
@@ VASwZì
åïçt§\IioêZ@næ\IÉæèPUZIoj
@@@@V[hZAÀ[A¬A¬cAçt
@@@@{ZÍêñíÅÖÉ12A|1ųµ½ªA
@@@@ññíÉÉÉsB
ºa25N
@@@V[YXAæ4ñú{w¶ì
¦ï¬LOåïiÖåïjªçtsÅJó꽪A
@@@»Ìçt§ã\èíªI²lZÅsíêA{ZÍð8A|2A¬ð6|5ÅjèA
@@@çt§ã\ƵÄ{åïÉoêµ½B{åïÅÍ«HÉ7|0Åsê½B
ºa25NV
@SwZì
åïçt§\IioêZ@næ\IÉæè32ZIoj
@V[hZ@çt¤A@¬cA@À[A@çt
@V[hlZÉ¿AìÖåïoê ð¾éB
@{ZÍAå½ìð17|0R[hAD´ð6|3A¶¤ð2|0ÅjèioB
@81A2A3úÌ\èÉÄìÖåïªçt§c
êÉÄJóêéB
@ÍPúAQúÍ\èÊèsí꽪AQúé©ç~è¾µ½JÍeÕÉ~ܸA~Þð¦¸qì®·ÙÉ«~ß³êé±ÆÉÈÁ½ªA»Ì·JÍ¢ÂãéÆ̩ʵª§½¸A¢ÉTúAê½ñA½µAVóÌñµ½VúÉ}«æíðs¤±ÆÉÈÁ½B
@ºàûKêðÂçtƪRÌ{ZÆÌsÍðRƵĢÄAbqðÚOɵÄ7|1Æ¢¤å·ÅsêÁ½ÌÅ éB
ºa25NH
@V`[ÉÈÁÄAsì{ä
êÅI²WZÉæéVlåïªJóêA{ZÍêñíÅÄÉø±«¶q¤ð5|0ÌXRAÅjAÅÍDèòð¬cÆÎíAçt§
jÉcé·21ñ̬ÌAsê½àÌÌÀÍÍ]¿³ê½B
ºa26N
@3A±ÌNbqI²åïÉoêªÜÁÄAÙRÅûKðµÄ¢½¾¡ZÉûKð§ÝA17A|1Ìå·ÅêRA»ÌÅüÍܳɳG̨¢ª Á½B
@4æ5ñú{w¶ì
¦ï¬åïçt§\IÅÍAhG¬cAðjÁÄAðNÉø±«DAÄÑÖåïÉîðiß½B{åïÅÍAn³«É14|0ųµ½ªAññíÅ_Þì¤HiãÌú{nåòĪå«Å Á½jÉ7|3Åüµ½B
@ºa26N5AtGÖZI²ì
åïçt§\IÅoêWZÌg[ig𿲫§ºåïÉDðüÁ½B
512úæè14úÜÅb{sÅJóê½ÖåïÉA{Zª§ã\ƵÄoêµ½ªAYaÉsê½B
7APáÌSwZçt§\IÅÍAtGåïDÌÀÑÉæÁÄAæêV[hÆÈèDòâÌMªÉ°çêAõê¯àKðúµÄoêµ½Bµ©µAXÅADèkìiãÉSAlÈÇÅôµ½jðÂAº²´É10|0Æ¢¤víÊåsðiµAbq̲Í¢É
AÉAµ½ÌÅ éB
ºa51N@SZì Iè çt§åï
| 1ñí | @@@@@@sí | ||
| 2ñí |
À[
|
3-1
|
çtì
|
| 3ñí |
À[
|
4-2
|
s´
|
| 4ñí |
À[
|
8-1
|
|
| 5ñí |
À[
|
11-1
|
çth¤
|
| |
À[
|
7-5
|
N¤i·12ñj
|
| |
À[
|
0-15
|
¶q¤
|
íÉͦÈcªÅ«A9äÌoXðAËÄÉsÁ½ªAG[XÎä誨ð¢½ßAÅüàå²ð«AÍs«Äåsðiµ½B