 |
| 昔の修学旅行… 平成28年12月2日 明治時代の大高生・・・当時をしのぶ資料が見つかりました。 当時の修学旅行は、学年により成田・銚子方面と房州方面への2コースありました。開校初年度の明治33年11月に清澄・勝浦方面、翌34年からは2コースになり、毎年11月に行っていたようです。明治30年代を通して見ますと、36・37年は記録がなく、39年からは東京湾を横断して浦賀まで行っています。 明治35年に実施された房州への修学旅行は、1年生が行ったようです。この時、引率した教師の一人である博物学の加藤鉄治郎教諭は、行程の各所でスケッチをし、「房州畫巻」としてまとめました。今回、先生のご家族のご厚意でそれを掲載させていただき、それに従って旅程を説明します。 初日は、大多喜-老川-清澄山-天津(泊)の険しい山越えの道を辿って海岸へ達します。1枚目の朝霧に包まれた山村のうつくしい絵は大多喜町紙敷、学校から峠を1つ越えた集落です。ここからさらに山を越えて養老渓谷へ入り、日蓮宗本山清澄寺から、天津の海岸へ出ました。 2日目早朝に天津を発って、天津-鴨川-白浜-那古-保田の海岸線沿いの道を歩いたという卒業生(故人)の談話があります。ただ、天津から保田まで相当の距離(おそらく100㎞以上)があると思われるので、白浜あたりで一泊したのではと推測されますが、白浜の絵を見るかぎり昼間の様子で、鋸山で夜になっているようです(調べれば、山とその時期の満月に近い月の位置関係から、11月何日の何時頃か推定できると思われる)。そうだとすると、天津から保田まで、一日で歩いたのでしょうか。これも非常に興味深いことです。 絵に描かれている旅行中の生徒の様子については、やはり卒業生の談話にあり、「羽織、袴、赤毛布(アカゲット)、白風呂敷、脚絆(キャハン)、草鞋(ワラジ)<1日2足>」であったということです。 |
|
 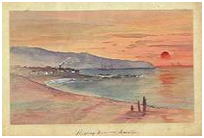 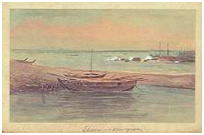 大多喜町・紙敷 天津港の日の出 鴨川漁港 |
|
 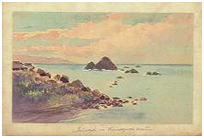 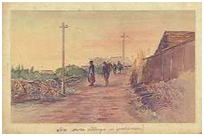 鴨川・松崎橋 鴨川・弁天島 江見・吉浦 |
|
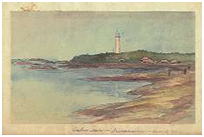 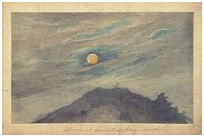  白浜の海岸 鋸山山頂の月 保田の海岸から富士を望む |
|
| トップページに戻る |