農業の担い手になるためには、農業に関する基礎的な知識や技術を学ぶ必要があります。そのためには、教室で農業の知識を学ぶとともに、県内各地の優れた農家の現場で、実際に農業を体験する中で知識や技術を身につけ、判断力や経営力を養うことが大切です。
専攻科では、プロジェクト学習、農家見学、先進農家研修、営農計画など実践的な学習を多く行い学習の効果を高めています。又、農業をしていくには協力しあえる仲間も必要です。そのために専攻科では仲間づくりが出来るような数々の場を設けています。
これらの目標を達成するために、専攻科では出校学習とプロジェクト学習を基本とした独自の方法を行っています。
○出校学習
月〜水は出校し、一般教養科目や農業専門科目を学びます。
一般教養科目・・・社会人として日常生活に必要な法律や経済などの基礎知識を学び、幅広い見方を養います。
農業専門科目・・・農業の担い手として必要な土肥料、病害虫、経営、情報など専門的な知識や技術を実験や演習を行いながら学習します。
この他、出校日には、農家見学や、交流会、相互研修なども行っています。



○プロジェクト学習
農業は実践を通して学ぶことにより、知識や技術を身につけることができます。木・金は家の農業を手伝いながら技術を覚えたり、経営を理解します。家の農業とは別の農業を学びたい場合や非農家の場合は、学校が個々の学生に相応しい農家を紹介します。農家で学んだ事は出校学習で理解を深めるようにします。




専攻科ではこの他に次のような実践的教育を行っています。
○先進農家研修
専攻科の学習の中で最も重要と位置づけている研修の一つです。個々の学生に相応しい研修先を紹介します。1年次に2〜3ヶ月間、県内外の優れた農家で栽培や飼育の技術とともに経営的な考え方を学びます。これまで北は福島から南は熊本までと全国各地で研修を行ってきました。宿泊が原則ですが通いでの研修も行なっています。農家と生活や農作業を共にすることで、社会勉強も出来ます。






○北海道農業研修
北海道士幌町の農家で約10日間生活を共にしながら、早朝から夕方まで大型農業機械を使ったジャガイモの収穫作業などを体験します。開拓の歴史を肌で感じることが出来ます。研修後は道内各地を旅行し、雄大な自然や文化に触れることができます。卒業後も農家と交流を続けている学生もいます。



○農家見学
毎年県内の野菜・草花・果樹・畜産の農家や流通施設などを約10カ所見学します。立地条件を生かした経営や、様々な工夫をしている経営者の姿に、自分も農業に取り入れてみたいという学生も現れます。見学先には卒業生もいて多いに力づけられます。



○営農計画の作成
将来どんな農業を経営したいかを考え、具体的計画を作成します。そのために経営環境や作物ごとの栽培方法、収支などを調べ、自家の現状をよく理解することから始めます。その中から課題を見つけ、対策を立てていきます。非農家の学生が農業をする場合は、土地や資金の問題がありますので、それらを十分考慮しながら計画を立てます。経営目標が出来るので、農業に対する意欲も向上します
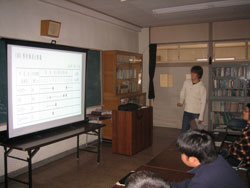
仲間づくり
農業をしていく上で仲間はとても大切です。専攻科では将来に亘って協力できる仲間を作るため、数々の場を設けています。
○相互研修
この研修は専攻科独自のものです。学生は県内各地から通学しており、経営内容も様々です。学生が家で自分の農業について発表し、質問や意見交換をしながら農業の勉強をします。卒業後、学生同士が農作業の手伝いをするということもあり、仲間づくりに大変役立っています。


○交流会
年に数回の交流会(レクリエーション)を実施します。学生の希望によって内容は変わりますが、ボウリング、潮干狩り、スポーツ大会などを実施しています。学生が個性を発揮出来親睦を深めています。


○学園祭
毎年11月の学園祭に参加します。以前は餅つきでしたが、最近は赤飯、豚汁の販売をしています。安くて美味しいので来校者にとても好評です。専攻科の卒業生も来校するので、交流の場にもなっています。

